どうも、猿人です。
今日は最近巷で流行りつつある残業キャンセル界隈について考えていこうと思います。
深刻な問題ですが解決策は必ずあると思います。
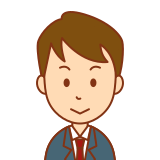
今日中にやってほしいことがおわってないのに定時で返ってしまう新人をなんとかしたいんだよね。。

最近このフレーズをよく聞くけど、相手がどう思っているのかを考えてみないと解決するのは難しいかもしれないね
まずは新人が何を考えているのかを考えてみる
最近の若いやつはというセリフは江戸時代からすでにあったようです。ということは今のベテラン上司がさらにベテラン上司に教わってさらに。。
というようにいつの世も若い人の行動は目上の人には滑稽かつ理解が出来ないことがあることは必然であると考えてみることで見え方は変わってきます。
Y世代からZ世代に移り、今はα世代が出てきています。その時代の人を否定していてもきりがありませんし、その人を変えていくこともマネジメントの一つです。
そうはいっても何を言っても理解が出来ない場合はどうすれば良いのかというケースもあるかと思いますが、なぜそう考えているのかを紐解くことが大切であると思います。
先日居酒屋を経営されている方の息子さんが夏休みで手伝いに店に出たけど全然使えないから店主がなんで手が空いてるなら率先して掃除をやったり出来ることをしないのかと叱責したらこう言われたというのです。
「同じ時給をもらっているなら言われたことだけやったほうがパフォーマンスがいいじゃん」と父親に言ったそうです。
それを聞いた私はなるほどと唸ってしまいました。確かにおっしゃる通りでぐうの音も出ないとはこのことです。
これが労働者の本音であると、そしてマルクスの共産主義がダメになった証明のようにも感じてしまいました。
人間の本質は怠惰であるのかもしれません。同じお金をもらうならなるべく働かないほうが得であるというバイアスが働いているのだと思いました。
それを親子だからこそ、なんの忖度もなく言えたあたりに使用人の本質の答えが垣間見えます。
ではその解決策はあるのか?
ではその解決策はあるのか?
それはシステムを変えるしかないのではないだろうか。仕事をタスク制にしてやった分にインセンティブを支払う、そうすることでやった分だけ給与に反映してくる。
そうすることで不公平感は減り、お店は色々なことを提案して売り上げアップの施策などが次々に出てくるのではないでしょうか。
しかしこれには先行投資が必要です。やったことに対して成果が出なくてもやった限りはそれに対するインセンティブが発生してしまうからです。
それに加えて最低時給でも満足という人が出てくると残業キャンセル界隈がまた蔓延してしまう可能性がぬぐえません。
であるならば本人が残業にならないように同じ内容の仕事を時間内にやってもらわなければなりません。
仕事のスピード感を上げてもらうのは新人にはなかなか難しいと思いますので、タスクのコントロールをこちらでしてあげる必要があると思います。企画書や提案書、データ分析などはあらかじめ、顧客から与えられた時間の管理を把握して無理のないスケジュールを組んでチームで共有する。
今はどこも人手不足で、働き方改革もあるので時間的な融通はききやすい時代になっていると思います。しっかりとクライアントとその時間管理を上司が詰めてから新人や若い人に下してあげることが出来ればそもそも残業を抱えることも減ってくるのではないだろうか。
そうはいっても突然の案件やトラブルはつきものであるという意見もあります。企業を運営しているとそんなことは日常茶飯事であるともいえます。
ですので突発対応はある程度想定の上でフレックスにして出勤時間を遅らして退社時間を遅くするなどでシフト化をして組織で対応することで乗り切るという手もあります。それならシフトなので遅い時間に出る突発の仕事もその時の遅番の人間で対応する。逆に朝一でのトラブルとうは早番が対応するなどの脱属人化にもつながり強い組織が出来るきっかけとなる可能性もあります。
大抵のことはコミュニケーションで解決できる
残業をしたくない理由はなんなのか、それを聞いてみることも上司の役割であると考えてみる。
もしかしたらしない理由があるかもしれません。人はその人その人に歴史があります。バックボーンを誰もが抱えて生きています。
ですからしっかりと話を聞いてその真意を紐解いていくことでそう考える本質が理解できるかもしれません。
もしかしらた家でケアが必要な人がいたり、奨学金返済のダブルワークをしていたり、様々な人には言えないなにかしらのものがあるかもしれません。
しかし今の新人を含め、若い世代は自分のことを自ら語ることは少ないように感じます。それは約20年前より始まった個人情報の取り扱いの厳格化にもあるように感じます。個人情報をうるさく言いだしてから個々の情報を容易に話したがらないし、聞いてはいけないというのが今の若い人にはしっかりと定着していて、そこが自らを語らないというひととなっているのかもしれません。
ですから上司はちょっとしたことからでもいいのでコミュニケーションをとっていくことで相手のことを理解していくことが大切です。
最近の若いやつはという雰囲気で構えているとなおさら若者は近づいてきませんし、心をひらくこともありません。
ではなぜそうなるのか?
今のコンプライアンスの厳しい時代に育った人は絶対に踏み外せないし、新しいことをするよりしないことのほうが安全であるというような心理になっているのは彼らのせいではなく、社会の構造の問題であると思います。
げんに仕事と関係のない人とは年配と若い人の垣根はないように感じます。それが業務という関係性が出来た瞬間に大きな壁が出来てしまうと思います。
まとめ
多くの人が働くことには意欲的であると考えます。一部の奇抜な思考がSNSによって独り歩きしているケースもよくみられます。ですのでしっかりと個々を見ることで若者すべてが働くことを嫌っているわけではないです。コミュニケーションをしっかりととることが上司も部下も双方にとって最善といえるでしょう。
では頑張っていきましょう!





コメント